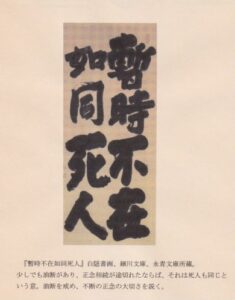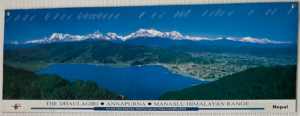本棚の整理をしていると、昔懐かしい1冊の本、「医学教育の原理と進め方」を見つけました。
たいへん型苦しいタイトルの本で、店頭に横積みされていても、今ならまず手に取ることのなさそうな本です。
文部省の富士研修所で
昭和64年1月に就任した新米教授の私は、文部省の富士研修所での医学教育セミナーに参加する命を受けました。丸一週間、朝から晩まで缶詰めです。夜抜け出そうにも、富士山麓の一面闇の世界です。
全国の医学部から教育担当者40名ほどが受講し、小児科教授は私だけ、顔見知りの方は一人もいません。当初は、学生の合コンのように、互いの親睦を深める意図で他愛ないゲームをさせられます。画用紙に似顔絵を描かされました。昨日まで大学で偉そうな顔をしていた連中がまるで子ども扱いです。日常生活とは大きなギャップです。
大学に戻れば、山ほど仕事があります。受講者からはブーイングです。でも、チューター連中は慣れたものです。我々が、次第に慣れてくると、グループ分けされ、毎日いろんな課題を与えられます。
ここで、「医学教育の原理」が現れます。問題解決型の思考法です。
一般目標(GIO)と行動目標(SBO)
当時の私にとっては全く耳新しいことばです。
一般目標(General Institutional Objective, GIO)とは、学習者が何をできるようになるかを総括的に記述したもので、教員と学生の両者への一般的なオリエンテーションとなるものです。例えば、「尿路感染症患者の診断と治療ができるようになるために、この疾患の微生物学的特性を理解する。」
行動目標(Specific Behavioral Objectives, SBOs)とは、個々の一般目標を達成するには、どのようなことができるようなればよいかを、具体的な行動の言葉で書き表したものです。
今日では、大学教育の中で問題解決型の思考法、GIO、SBOは当たり前になっていると思いますが、それまでの医学教育では個々の教授が思い思いに一方的に講義していました。
セミナーでは、連日新しい、大きな課題が与えられ、数班に分かれて意見を出し合い、GIO、SBOを適切に立案するのが目的でした。いつの間にかチューターの思い通りに動いていました。
何にでも役立つPDCAサイクル
この問題解決型の思考法の基本になっているのがPDCAサイクルです。何ごとも評価があって次のステップへ、新しい目標設定が始まるのです。
この考え方は、ビジネス分野から始まったようですが、教育分野、研究分野においても大いに役立ちます。
囲碁においても同じです。いくら優れたプランを立てて盤に向かっても、相手の応対でその妥当性を評価しながら、ACTION(改善)を起こさないと勝利に結びつきません。
私の脳にこのときに叩き込まれたPDCAの思考回路は、何ごとをするのにも絶えず役立っています。
CHECK(評価)が欠けると悲劇を招く
最近のビジネスでは、時代の流れが早すぎて、いちいちCHECK(評価)して次のステップに進んでいると時代遅れになると、あまりPDCAを守らなくなっているようです。
トヨタ自動車のカイゼン・プログラムは世界的に有名で、米国の経営者が名古屋を訪れ、学んでいました。でも、あのトヨタが品質管理面での不正を行う時代になったのです。私にとって大きなショックです。
これは、トヨタだけの問題ではなく、名のある大企業や私にとって身近な医学分野にも、当人たちが意識していなところで及んでいるのではないかと内心危惧しています。
あまり目先のことばかり考えて、足元をしっかりと見つめてないととんでもない悲劇を招きそうです。 2024.9.7.