もうすぐ夏休みです。涼を求めて六甲山に家族で登る計画を立てておられる方も多いかと思います。山登りにおいて、最も出会う確率が高い危険な生きものがスズメバチです。スズメバチは、ハチの中でも比較的大きく、かつ攻撃的で、猛毒を持っています。
スズメバチが襲うのは
スズメバチは、木の洞や土の中、建物の軒下などに巣を作ります。中でも、土の中に巣を作るオオスズメバチは、最も危険で、絶対に近づかないことです。ハイキングコースの近くに巣を作ることが多々ありますので、注意が必要です。
スズメバチが攻撃してくるのは、自分たちの巣を守るためで、何もしなければ襲ってくることはありません。つい手で払ってしまったり、あるいは気づかずに巣に近づいてしまった場合など、ハチを警戒させてしまったときは、姿勢を低くして、ゆっくりとその場を離れてください。決してそれ以上ハチを刺激しないようにしてください。
ただし、一度でも刺されてしまうと、毒液の匂いによって他のハチまで攻撃的になり、集団で攻撃してくる危険性が高くなります。その時は、走ってでも速やかにその場から離れることです。
スズメバチに刺されてしまったときは
まず刺された場所から離れ、水で傷口を洗い流しましょう。手で毒液を搾り出すようにすれば、毒を薄める効果が期待できます。口で吸い出さないように。
もし、刺された後に全身の震えや発疹、吐き気、嘔吐、めまいなど、アナフィラキシー・ショックの症状が出たときは非常に危険です。これらの症状は刺されてから30~60分以内に出ることが大半です。症状が出たときは、一刻も早く救助を要請しましょう。
ハチ毒によるアレルギー反応
スズメバチによる死亡は、毒の直接作用によるものは極めて稀で、ほとんどがハチ毒によるアレルギー反応(アナフィラキシー・ショック)によるとされています。その危険性は、子どもよりもお父さんの方が大です。
死亡例は50歳以上で、若年者の死亡例は全くみられないと言われています。その理由として、若年者は刺された累積回数が少なく、アレルギー抗体の産生が不十分で、免疫反応が起こり難いため、アナフィラキシー・ショックに至りにくいと推測されています。
2022.7.20.
参考:神戸市HP、「六甲山に登る皆さまへ」という、登山者への注意事項の一つとして、スズメバチへの対処方法等が詳しく記載されています。

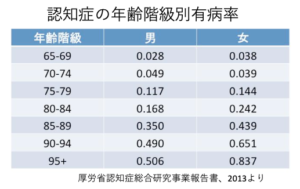

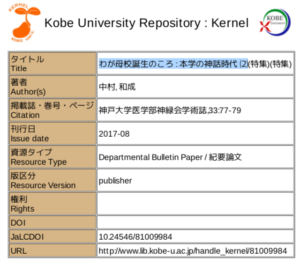


 このシンボルマークは「スリーアギトス」と呼ばれています。「アギト(agitō)」とは、ラテン語で「私は動く」という意味で、困難なことがあってもあきらめずに、限界に挑戦し続けるパラリンピアンを表現しています。赤・青・緑の三色は、世界の国旗で最も多く使用されている色ということで選ばれたそうです(日本パラリンピック委員会ホームページより) 。「仮面ライダーJ」の登場人物として、架空の人名アギトが用いられています。
このシンボルマークは「スリーアギトス」と呼ばれています。「アギト(agitō)」とは、ラテン語で「私は動く」という意味で、困難なことがあってもあきらめずに、限界に挑戦し続けるパラリンピアンを表現しています。赤・青・緑の三色は、世界の国旗で最も多く使用されている色ということで選ばれたそうです(日本パラリンピック委員会ホームページより) 。「仮面ライダーJ」の登場人物として、架空の人名アギトが用いられています。