コロナウイルスの自然宿主として主要な動物種はコウモリです。COVID19の流行と中国武漢のコウモリとの関連性が当初指摘されていましたが、未だに定かではありません。
COVID19と関連付けられている重症急性呼吸器症候群(SARS)と中東呼吸器症候群(MERS)もコウモリを自然宿主としています。
鳥なき里の蝙蝠(コウモリ)
コウモリは、空中を飛べる唯一の哺乳動物です。
今日では、稀有種は珍重されていますが、獣でもなく、鳥でもないコウモリを、昔は一段低く見ていたようです。
「鳥なき里の蝙蝠(こうもり)」とは、にせもの扱いの喩えで、すぐれた人がいないところでは、つまらない者がわが物顔をして威張ることを言います。
多くのコロナウイルスを保有するコウモリ
多くの動物がコロナウイルスを保有していますが、コウモリは特に多くのコロナウイルスを保有しています。1万匹のコウモリから91種類のコロナウイルスが分離できたという研究もあります。
コウモリは、コロナウイルス以外にも、エボラウイルスやマールブルグウイルスなどさまざまなウイルスを保有しています。エボラウイルスとマールブルグウイルスは、エボラ出血熱とマールブルグ出血熱の原因ウイルスで、COVID19よりもはるかに致死率が高い病気です。
マールブルグ病とは
国立感染症研究所の直近の感染症情報(2023年3月7日付)として、ウイルス性出血熱のひとつであるマールブルグ病が取り上げられています。
この疾患はエボラ出血熱と同様に、高病原性のウイルス感染症で、ケニア、コンゴ、ウガンダなどのアフリカの国々で症例が確認されています。この名称の由来は、ドイツのMarburgで最初の症例が確認されたことによるものです。
動物のウイルスが人に感染し、それが人から人へと広がるのは稀
COVID19は、動物に感染していたコロナウイルスが人に感染したことから始まりました。通常、動物のウイルスが人に感染し、それが人から人へと広がることはありません。
しかし、COVID19のように、変異した動物ウイルスが人に感染し、人に適応して、人から人へと広がっていくことがまれにあります。
A型インフルエンザウイルスがコウモリに
高病原性の鳥インフルエンザが、日本国内でも猛威を振るっています。発生が確認された養鶏場や、処分されるニワトリなどの数も過去最多を更新しています。
鳥インフルエンザの原因ウイルス、A型インフルエンザウイルス「H5N1」は、鳥類で起きる感染症と考えられていましたが、最近、コウモリにおいても発見されています。
高病原性の鳥インフルエンザウイルスが、コウモリにおいて変異し、哺乳動物への伝播が起きないことを願っています。
2023.3.15.

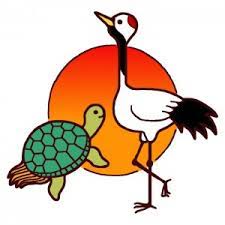 2023.2.8.
2023.2.8.