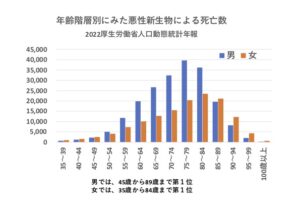朝起き、六甲山を見上げると、澄み切った青空に山頂の展望台がくっきりと近づいて見えます。
このところ、私の頭の中はあるのは、来年の熱中症対策をいかにするかです。同世代の友人に電話し、お互いに情報交換し、慰めあったり、励ましあったりしています。その中で上がってきたアイデアを整理してみると、
来年の熱中症対策をいかにするか
基本的には、暑さの最も厳しい7月下旬から8月中旬のお盆過ぎまでの1ヶ月間をいかに乗り切るかです。
第1案。北海道の遠軽町にあるリゾートホテル「マウレ山荘」
旅行好きの情報通の友人山崎君が教えてくれたのが北海道・遠軽町の丸瀬布の森の中に佇むリゾートホテル。アクセスは札幌からJR石北本線で3時間。アルカリ性単純泉の温泉が湧き出ています。
「心地よい風と木漏れ日の中で、ゆったりとくつろぐ贅沢なひとときを 過ごしてみませんか。」がキャッチコピー。でも、ここで1ヶ月間独りで過ごすのは、かなり無理がある気がします。

第2案。札幌中心街のホテル
1ヶ月間退屈せずに過ごすには、近隣に囲碁クラブがある場所なら問題ないことに気づきました。それなら、大都会の方が良かろうと、札幌市内の囲碁クラブをチェックしたところ、すすきの駅近くにあることがわかりました。
すすきの駅界隈なら、手頃なホテルが数多くあり、食事に困りません。有力な候補地です。

第3案 ワルシャワ
1ヶ月ぶりに、囲碁クラブ「方円」で関西棋院プロの村岡茂行九段の指導碁を受けてきました。
村岡茂行プロは大変な国際派で、今夏は2週間余り、フランス南部の町、トゥールーズで行われた「ヨーロッパ碁コングレス」に、奥さんの美香プロとがアマチュアの日本人の囲碁ファンを引率して、出席されました。
ヨーロッパ各地から多数の囲碁ファンが集まり、出席者は数百名に及び、2週間にわたって賑やかに対局されたそうです。
ワルシャワでの囲碁国際大会への出席
その大会が、来年はポーランドのワルシャワで開催されるそうです。開催時期も7月末から8月中旬まで、ちょうど私が探し求めていた避暑地として最適です。
ワルシャワの8月の最高気温は22〜23℃くらい、日本の春の気温です。
ここでなら、2週間退屈せずに過ごせそうです。来年への大きな目標ができました。
フィンランド航空では、2025年度のスケヂュールでは関空からヘルシンキまでの直行便が週5便就航するようです。久しぶりの海外旅行、体力づくりに励まなくては。
娘には、しっかり保険をかけていくようにと強く言われています。
もうひとつの難題は、ロシアとウクライナの和平です。これも解決していそうです。
 2024.9.5.
2024.9.5.