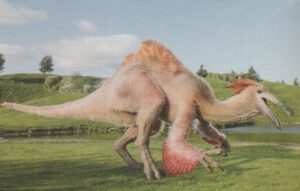アリの嗅覚についての研究の第一人者である昆虫学者の尾崎まみこ教授から、予期せぬ原稿依頼がありました。先生が編集中の「動物の生きるしくみ図鑑」で、「愛着、養育」という章で、”まなかい”という言葉を是非とも取り上げたいとの思いから、以前私が「子育てをもっと楽しむ」の中で、この言葉を取り上げていたことを思い出され、執筆依頼が舞い込んだ次第です。
私自身も、この“まなかい”という語感が大好きです。赤ちゃんと見つめ合っていると思わず吹き出してしまいそうになります。お母さんと赤ちゃんが見つめ合い、微笑む姿を見ると、こちらまでつられて微笑んでしまいます。
ヒト新生児には表情の模倣という行為が生得的に備わっている
生まれて間もない赤ちゃんの目の前で、大人が舌を突き出したり、口を開閉しながら微笑みかけると、赤ちゃんはこちらの表情を鏡に映し出すようにまねます。ヒトの新生児は、他哺乳類と違って、自力で母親にしがみつけず、母親の手助けなしにはおっぱいを飲めません。
誕生したときから、他者、母親の関心を引き、世話をしてもらわないと生きていけないので、表情の模倣という行為が、ヒトでは生得的に備わったと考えられています。
育児の神様といわれる大先輩の小児科医、内藤壽七郎先生は、「育児の基本は、“まなかい”にある」と絶えず話されていました。広辞苑には、まなかい【目交ひ/眼間】とは、目と目の間、眼の前と記されているだけですが、先生は「目と目が合うこと」、アイコンタクトの意味で使っておられます。
単に目と目が合うというだけでなく、見つめ合いや微笑を通じての母と子の「快の情動」が、周りの人にまで伝わってきます。
尾崎まみこ教授は、ヒト乳児の頭の匂について神戸大学小児科の永瀬裕朗教授らと共同研究を行っておられます。研究室にはタイミングよく出産を間近に控えた女性医師が二人おられ、ご協力を得て現在研究が進行中です。母乳栄養児が離乳食を取り始めるとどのように変化していくのか、興味は尽きません。
2023.5.11.
試しにChatGPT君に英訳してもらいました。
“The Healing Power of ‘Manakai’ – How Babies Soothe Adults”
I received an unexpected manuscript request from Professor Mamiko Ozaki, a leading researcher in the field of ant olfaction. She is working on a section titled “Attachment and Nurturing” for the upcoming “Illustrated Guide to Animal Behavior” and wanted to include the term “manakai” which I had previously discussed in my book “Enjoying Child Rearing”.
I myself also love the sound of this word “manakai”. When I see a mother and baby looking at each other and smiling, I can’t help but burst into laughter. It’s contagious and makes me smile too.
Infants are born with an innate ability to mimic facial expressions. When an adult smiles or sticks out their tongue in front of a newborn, the baby mimics the expression back as if reflecting it in a mirror. Unlike other mammals, human newborns are unable to cling to their mothers or nurse without assistance.
From birth, infants require attention and care from others, especially their mothers, to survive. It is believed that the act of mimicking facial expressions is innate in humans because it is necessary for survival.
Dr. Jushichiro Naito, a senior pediatrician known as the godfather of child-rearing, constantly emphasized that “the basics of child-rearing are found in ‘manakai'”. While the dictionary simply defines “manakai” as “the space between the eyes”, Dr. Naito used it to mean “eye contact”.
Not only does “manakai” refer to the act of making eye contact, but it also refers to the “pleasurable emotional connection” between a mother and child through shared gazes and smiles, which can be felt by those around them.